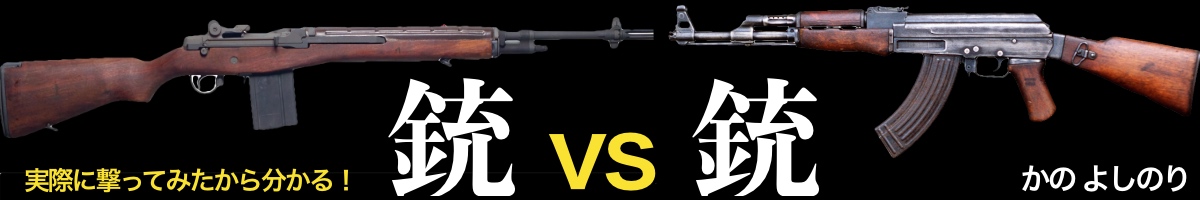
今回は、19世紀末に開発され、日露戦争でも使用された日本とロシアの回転式拳銃(リボルバー)を取り上げる。リボルバーは16世紀には存在していたが、19世紀中期にはダブルアクション機構も普及しつつあり、基本構造は完成の域に達しつつあったとされる。
日露戦争〜第二次世界大戦期の拳銃
26年式拳銃(以下、26年式)は明治26(1893)年に制定された日本軍の国産拳銃であり、日露戦争から第一次世界大戦、そして第二次世界大戦では旧式化して第一線装備ではなくなったものの、なお補助的には使われていた。
ナガンは1895年制式のロシア軍の拳銃だ。日露戦争、第一次世界大戦、そして第二次世界大戦のときには旧式化して第一線兵器ではなくなっていたが、補助的に使われていたというわけで、日本とロシアの、同じ世代の軍用拳銃である。
筆者は日本人なのだから、タイムスリップして日露戦争に参戦するとしても日本軍に参加するしか選択肢はないから、当然26年式を使うことになるが、「いや、26年式でもナガンでも、どちらで選んで使っていいよ」ということになった場合、どちらを選ぶか、悩んでしまう。

口径は26年式のほうが大きいが、威力は残念レベル
ナガンは口径7.62mm、26年式は口径9mm、口径だけを見れば26年式のほうが強力そうな印象を受けるが、26年式は実は軍用拳銃とは思えないほど低威力なのだ。9.8グラムの弾丸を秒速150mで発射するのだが……おいおい150mって、火縄銃の弾より遅いじゃないか。
現代の銃弾は鉛の弾丸(コア)を銅の皮(ジャケット)で包んだ構造をしている。鉛だけでは命中の衝撃で砕けたり潰れたりして貫通力がなくなるからだ。ところが26年式の弾は、あまりに速度が遅いので銅のジャケットで包んでいなくても、鉛だけの弾丸が変形しない。
その威力は6.3gの弾丸を秒速271mで発射するナガンの3分の1なのである。そのナガンの威力さえ少々威力不足ぎみで、かの怪僧ラスプーチンはこれを5発撃ち込まれて死なず、川へ投げ込まれて溺死したというくらいなのである。
その3分の1の威力しかない拳銃だ。二・二六事件1のとき、鈴木貫太郎は26年式拳銃で至近距離から3発撃ち込まれて、死ななかった。

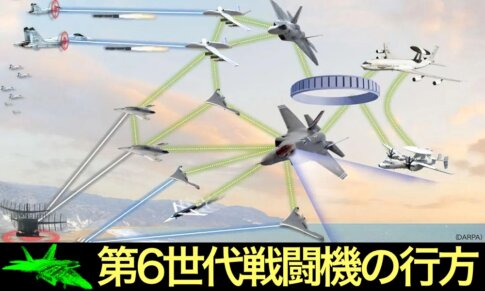










コメントを残す